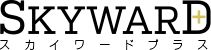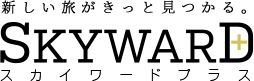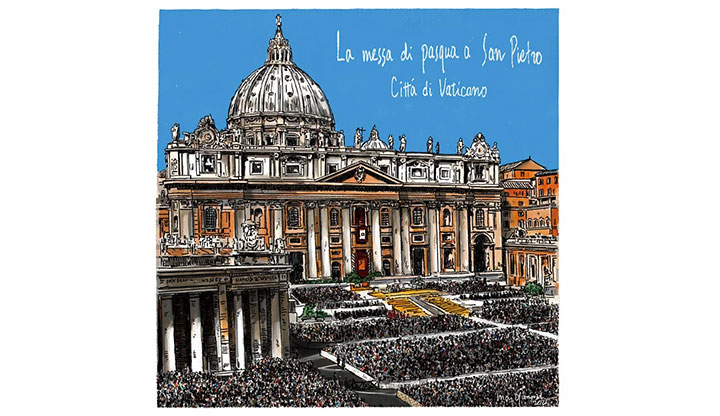秋の気配を感じる頃、よく耳にする「神無月」。かんなづき、かみなしづきなど、いくつかの読み方がある。
神無月はいつで、どんな意味があるのだろうか?
そんな疑問にこたえるべく、本記事では
・神無月っていつ?
・神無月の名称の由来
・出雲の行事
・全国各地の行事
・神無月の和菓子
などについて解説する。
▼あわせて読みたい人気記事
日本全国パワースポット13選|2025年下半期の運気を上げよう!
目次
神無月って何?

「神無月」とは、旧暦(陰暦)の10月を指す和風月名(わふうげつめい)だ。
「和風月名」とは旧暦の季節や行事に合わせた呼び名であり、ほかにも、3月「弥生(やよい)」、6月「水無月(みなづき)」、8月「葉月(はづき)」、12月「師走(しわす)」など、12カ月のそれぞれに呼び名がある。
なお、旧暦とは、明治6(1873)年に太陽暦(新暦)が採用されるまで使われていた「太陰太陽暦」のこと。月の満ち欠けをもとに季節を表す太陽の動きを加味して作られた暦で、新月になる日を各月の始まりと考えた。一カ月の長さは、新月から新月までの約29.5日となる。
神無月っていつ?
旧暦の10月を指す神無月だが、実は現在の新暦に直すと11月末頃にあたる。
しかし、今日では新暦10月の異称として用いられることも多い。カレンダーなどで見かけたことがある人もいるのではないだろうか。
ちなみに、旧暦10月の別名は他にも。
・開冬(かいとう)
・初霜月(はつしもづき)
・時雨月(しぐれづき)
・小春月(こはるづき)
・良月(りょうげつ)
・陽月(ようげつ)
など、季節を表すさまざまな呼称が存在する。また、出雲地域では「神在月(かみありづき)」と呼ばれている。
語源や由来を解説
つぎに「神無月」の語源や由来を見てみよう。いくつかの説がある。
神無月の「無」は「ない」ではなく、連体助詞「の」にあたるため、神無月=「神の月」といわれる。同じく和風月名の「水無月」の「無」も同様だ。
また、日本各地の八百万(やおよろず)の神が、この月に出雲に集まり、各地の神様が留守になるため「神無月」ともいわれる。諸社に祭りのない月であるから、という説もある。
そのほか、雷の鳴らない「雷無月(かみなしづき)」や、その年に新しくとれた穀物でお酒を造る「醸成月(かみなしづき)」、稲を刈る「刈稲月(かりねづき)」という説もある。
和風月名「水無月」についても知りたくなったらこちらを!
出雲の行事・風習

出雲では「神在月」という
島根県・出雲地方では、神無月のことを「神在月」という。日本各地から神々が出雲に集まり、会議「神議(かみはかり)」をするといわれている。
そのため出雲大社をはじめ出雲の神社では、神様を迎える「神迎祭(かみむかえさい)」、そして「神在祭(かみありさい/じんざいさい)」、神々をお見送りする「神等去出祭(からさでさい)」が行われる。
出雲大社のほか、出雲市の日御碕神社、朝山神社、万九千神社、松江市の熊野大社、佐太神社、神魂(かもす)神社、多賀神社などは諸国の神々が立ち寄るといわれ、神在祭が行われている。

神迎神事・神迎祭
出雲大社の西方約1km、稲佐の浜で行われる。かがり火を灯して全国からの神々をお迎えする神事(かみごと)で、「龍蛇(りゅうじゃ)神」に出雲大社まで導かれる。出雲大社では、境内の十九社が神々の宿泊所となる。
観光イベントではないため観客席などはない。見学する場合は、稲佐の浜に敷かれた、神様の通り道である菰(こも)の上を歩かないよう注意してほしい。むやみに撮影したり、フラッシュを使用するなど、神事の妨げにならないようにしたい。
神迎神事・神迎祭
2025年11月29日(土)
※旧暦10月10日
神在祭

出雲大社の「神在祭」では、全国の神々の会議「神議(かみはかり)」が行われるという。人があらかじめ知ることのできないこと、人の縁にかかわる万事諸事について決められるといい、男女の結びもそのなかの一つ。
なお地元の人たちは、神議のさまたげとならぬよう、神在祭の間は静かに謹んで過ごすという。神在祭に一般の人は参列できない。
出雲大社の神事は公開されていない場合も多いが、神事の期間も大社への参拝は可能だ。参拝の作法は、出雲大社では「2礼4拍手1礼」。
神在祭
2025年11月30日(日)・12月4日(木)・6日(土)
※旧暦10月11日・15日・17日
縁結大祭
出雲に集まった神々は、旧暦10月11日から17日にかけて、人々の幸せのご縁を結ぶという「神議(かみはかり)」を行うという。そして「縁結大祭」がお祭りに併せて行われ、さらなる幸せな縁結びを祈る祝詞がささげられる。
出雲大社には、全国から多くの人々が良縁を求めて訪れる。「縁結大祭」は一般の方も参列が可能。申し込み方法などの詳細は出雲大社のHPでご確認を。
縁結大祭
2025年12月1日(月)・4日(木)・6日(土)
※旧暦10月15日・17日
神等去出祭
神様をお送りする「神等去出祭」。出雲大社で行われた後、神々は斐川町の万九千神社で直会(なおらい)をし、お帰りになるといわれている。
本神事は一般の観光客には非公開の箇所もある。むやみに撮影したり、妨げにならないよう注意してほしい。
神等去出祭
2025年12月6日(土)
※旧暦10月17日
なお、今年の神在祭についてさらに詳しく知りたい方は、こちらもご参照いただきたい。
出雲大社 令和7年神在祭
URL:出雲大社Webサイト
全国各地の行事・風習

出雲へ神様を送り出す「神送り」
全国から出雲に向かう神様を送り出す「神送り」は、地域や神社によって異なるが、ほとんどが旧暦10月1日、それ以外なら9月末に行われることが多い。
神送りの日、地域の神社や各家庭では、旅立つ神様のために餅や赤飯を準備し、道中のお弁当として供える。また、出雲への手土産として団子を作りお供えする地域もある。夜遅くまで太鼓を打ち鳴らし、出雲へ発つ神様を見送る風習もあったそうだ。
古くは、収穫が終わり、田の神が山へと帰るのを送る祭りだったともいわれ、地域によって時期が異なる。また、この時期に吹く風を「神渡し」「神送り風」と呼ぶことも。この強い風に乗って、神様が出雲に向かうと考えられていた。
出雲からの帰還時に行う「神迎え」

出雲から戻ってくる神様をお迎えする「神迎え」。地域や神社によって異なるのだが、旧暦の10月の晦日(みそか)から11月1日ごろに行われる場合が多く、神様によってお迎えする時間帯も違う。餅や里芋などが供えられる。
また、旧暦11月1日を「神迎えの朔日(ついたち)」として、赤飯とお神酒で神様の帰還を祝う地域もある。
留守を守ってくれる神様

神々が出雲に出かけている間、出雲には行かずにとどまり、守ってくれる留守神(るすがみ)がいる。屋敷や竈をまもる荒神(こうじん)、恵比寿(恵比須)神、大黒(だいこく)、亥子(いのこ)の神などが知られている。
また、恵比寿神の「えびす講」は、神無月の10月20日や11月20日に行われることが多い。
神無月の和菓子
季節の行事と深いつながりをもつ和菓子。この時期に食べられる和菓子にはどんなものがあるのだろう?
神在月ゆかりの「ぜんざい(神在餅)」

神無月の和菓子といえば、出雲地方の「神在祭」でふるまわれる「神在(じんざい)餅」。この「じんざいもち」が出雲弁で「ずんざい」と呼ばれ、さらに「ぜんざい」となって京都に伝わったといわれる。
ぜんざいは、一般的にお餅や白玉団子などを甘く煮た小豆に合わせたもの。出雲では、紅白の丸い餅が入り、小豆は汁が多め。なお、10月31日は「出雲ぜんざいの日」!
亥の子(いのこ)餅

神無月のお菓子といえば、もう一つ。「亥の子」の日に、無病息災を願っていただく「亥子餅」がある。お餅や求肥にあんを包んできなこをまぶし、うり坊に見立てたものが多いが、地域やお店によって、さまざまな「亥の子餅」がある。
なお、亥の月とは旧暦10月のこと。亥の月の最初の亥の日の亥の刻(午後9~11時頃)に「亥の子餅」を食べると無病息災でいられるという。ちなみに2024年の亥の日は11月7日だ。
深まる秋の風情を感じ、巡る季節に感謝を
月の満ち欠けを感じていた旧暦の時代、収穫への感謝。八百万神(やおよろずのかみ)が出雲に集まるという、壮大な神事がいまも引き継がれていることの尊さ。
「神無月」について知るほどに、日本の歴史や文化も深く感じられたのではないだろうか?
巡りゆく季節、そして命をつなぐ収穫のサイクル、人智を超えた自然への畏敬の念と感謝の想い。旧暦10月をしめす言葉から、こんなにも世界が広がっていく。
今年も「神無月」を迎えられる喜びを、ぜんざいや亥の子餅を味わいながら、ぜひ感じてみてほしい。
関連記事