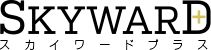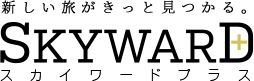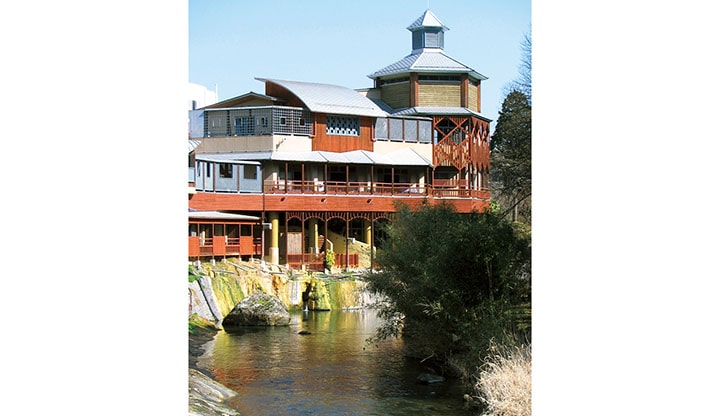夏の夜空に明るく輝く3つの星は、夏の大三角とも呼ばれる。この3つの星のうち、こと座のベガを織姫、わし座のアルタイルを彦星とする伝説は、日本人にとって馴染みが深い。
この伝説をもとに催される行事が、七夕(たなばた)である。五節句の一つでもある七夕は、日本において古くから人々に親しまれ、七夕に行われるお祭りを楽しみにしている人も多い。今回は、そんな七夕の歴史や由来、七夕にまつわる風習や食文化について紹介していこう。
▼あわせて読みたい人気記事
【2024年】7月24日と8月5日は土用の丑の日|うなぎを食べる意味や風習
目次
現代につながる七夕の長い歴史
七夕と聞いて、すぐに織姫と彦星の物語を思い出す人は多いだろう。それほどこの物語は広く知られている。七夕の夜には、空で年に一度会うことを許された織姫と彦星が再会を果たし、人々は願い事を書いた短冊を笹に飾り祈る。
今でもそのように七夕を過ごしている人は決して少なくないはずだ。では、そのような習わしや言い伝えは、どのように広まったのだろうか。
もともとは中国の伝説だった織姫と彦星の物語

「天の川のそばに住む天の神には、織女(しょくじょ)という娘がいた。織女は神々の着物を織る仕事をし、恋人を探す暇もないほど忙しく働いていた。それを見かねた天の神は、天の川の向こう岸で天の牛を飼っている働き者の若者、牽牛(けんぎゅう)と織女を結婚させた。
二人は夫婦仲良く毎日楽しく暮らしたが、仲が良いあまりに仕事を忘れ遊びほうけるようになった。それに怒った天の神は、二人を引き離して別々に生活させたが、二人があまりにも悲しそうにしているので、1年に一度、7月7日の夜だけ会うことを許した」
これが、七夕にまつわる中国の伝説である。中国には旧暦の7月7日の夜に織女星と牽牛星を祭る「二星会合の祭り」という催しがあった。
それとは別に、織女の祭りとして裁縫などの上達を願う「乞巧奠(きっこうでん)」という行事が存在した。どちらも織女に関係しているということで、二つの行事は次第に一緒に行われるようになった。
その習わしが奈良時代に日本へ伝えられ、一説には日本にもともと存在していた「棚機津女(たなばたつめ)」の伝説と結びついて宮廷や貴族に広まったといわれている。その後、江戸時代ごろには五節句の一つとして、七夕の行事と共に織姫と彦星の伝説も庶民に知られるようになった。
そして、織女星にお酒や食物を捧げ、女の子たちが習字や裁縫が上手になるようお祈りする「七夕(しちせき)」として徐々に定着していったのだ。
短冊に願い事。その起源とは?

七夕の定番の習わしは、願い事を書く短冊であろう。この短冊のルーツは、先にも述べた乞巧奠にあるといわれている。
乞巧奠は元来、織女星に手芸や芸能の上達を祈願する中国の行事。奈良時代に渡来人よりその風習が日本の宮廷へ伝えられた際、織女星への祈りの形として笹竹に五色の糸をかけたことが、短冊の起源とされている。
のちに五色の糸は絹の布へと変化したが、江戸時代ごろに庶民へ普及した際には、高価な布ではなく紙を用いるようになった。
五色の短冊が持つ意味とは?
童謡「たなばたさま」の歌詞に「ごしきのたんざく――」とあるように、短冊は五色というのが本来である。しかし単に5種類の色を使えばよいというわけではなく、使う色にはそれぞれ意味があり、願い事の内容によって短冊の色は決められている。
また、五色は中国の春秋戦国時代に生まれた「五行説」と「陰陽説」が組み合わさった「陰陽五行説」に基づくもの。この陰陽五行説は日本のさまざまな文化に影響を与えており、七夕の短冊もその一つというわけだ。

まず、短冊の色は「青・赤・黄・白・黒」。それぞれの色が陰陽五行説の「木・火・土・金・水」を表し、さらには五徳という教えにもあてはめられる。ただ、昔は緑を青と呼んでいたこと、紫が高貴な色とされていたことから黒が使われなくなり、近代では「緑・赤・黄・白・紫」が一般的とされている。
緑(青)は「仁」。周りへの愛や人間力を高めたいときに使う色といわれている。短冊には、周りの人のためになるような願いや自分の成長につながる願いが適しているとされる。
赤は「礼」。親や祖先への感謝や敬意を表す。短冊には、相手への感謝の気持ちを書くとよいそうだ。
黄は「信」。人間関係や信頼を表し、物事が継続するように願うのがよいとされていている。家族や夫婦の円満が叶いやすい色とも。
白は「義」。規則や義務を守る心を表す。人としての正しい道を願うときに意識したい色だ。
紫(黒)は「智」。学力の向上を表すため、学業成就や理解力、判断力向上などの願いを書くのがよいとされる。
このように短冊の色にはそれぞれ意味があるため、色に見合った願い事を書くことで、より成就に向けた決意を込めたものとなるだろう。
七夕にまつわる、さまざまな食文化
五節句の一つでもある七夕。五節句はもともと、季節の旬の植物を食べることで邪気を祓う日とされる。「七夕(しちせき)の節句」とも呼ばれる7月7日も節句の食べ物が存在する。
七夕は旧暦では8月中旬ごろとなるため、本来は祖霊を祭る「お盆」に入る前の物忌みの儀礼を行う日でもあった。そのことから、お盆にまつわる食文化を残す地域や、実際に月遅れの8月7日に七夕を催す地域もある。
では具体的に、日本には七夕にまつわる食べ物にどのような風習があるのだろうか。
七夕にそうめんを食べる理由

七夕の行事食としてよく知られている、そうめん。「天の川に見立てて食べる」という説もあるが、もともとは七夕が中国から伝来した際に、共に言い伝えられた「索餅(さくへい)」がそうめんの起源であるとされている。
索餅は中国に伝わるねじり菓子で、中国には「七夕に索餅を神様にお供えし、無病息災を祈る」という風習があった。油を塗ってひねり乾かした索餅は、そうめんと形が似ていた。さらに、そうめんが織姫を連想させる織り糸に似ていたことから、徐々にそうめんが供えられ、食べられるようになったという。
8月中旬はお中元の時期と重なる地域も多く、お中元にそうめんがよく贈られることも、このエピソードに由来するそうだ。
ちらし寿司は祝い事の定番料理

七夕にちらし寿司を食べる家庭は少なくないが、実は七夕にまつわるちらし寿司の由来は特に存在しない。
そもそも日本には昔からお祭りや祝い事の日にはお寿司を食べる習慣があった。
例えば海のない地域では山菜や野菜を酢飯と交互に敷き詰めた「角寿司(かくずし)」と呼ばれるもの、漁業が盛んな地域では「棒鮨(ぼうずし)」や「ばら寿司」など魚介を使ったものなど、具材や作り方は地域ごとに異なるが、確かにハレの日にお寿司を食べる習慣は全国各地にある。
そのため、五節句が祝い事の日と広く認識されていくとともに、お寿司を食べる習慣が根づいていたのではないかと考えられている。
長野県が育んだ「七夕ほうとう」という食文化

長野県の特に松本市周辺には、七夕にほうとうを食べるという風習が今でも存在する。ほうとうといえば、山梨県の郷土料理として知られているが、松本市の「七夕ほうとう」は違う。
七夕ほうとうは、ゆでたほうとうを水にさらしてほぐし、きな粉やゴマ、小豆餡を絡めたもの。今は決まった日に食べられていないが、もともとはお盆を迎えるために8月7日の朝、先祖代々の墓掃除の後に食されていたという。
正確な由来は文献などが残っておらず不明とされているが、小麦の収穫時期でもあったため、それを祝って食べ始めたのではないかといわれている。農林水産省のWebサイトでも紹介されているので、興味がある方はチェックしてみてほしい。
農林水産省「うちの郷土料理」
URL:https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/tanabata_houtou_nagano.html
織姫と彦星への特別なご馳走ともいわれている七夕ほうとう。これを供え食すると、松本の人々はお盆の訪れを感じるのだという。
七夕の由来を意識して過ごしてみよう
短冊に願い事を書いたり、そうめんをすすったりと、現代の日本でも、身近な行事として定着している七夕。その歴史を振り返ると、1000年以上も前に中国から伝わってきた文化は少しずつ形を変え、日本独自の文化として根づいていったことがわかる。
これまで何となく過ごしていた七夕も、一つ一つの由来や意味を意識すれば、今年は少し違った過ごし方ができるかもしれない。
関連記事